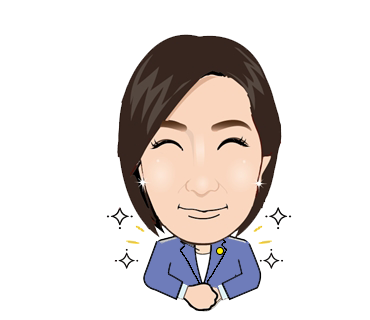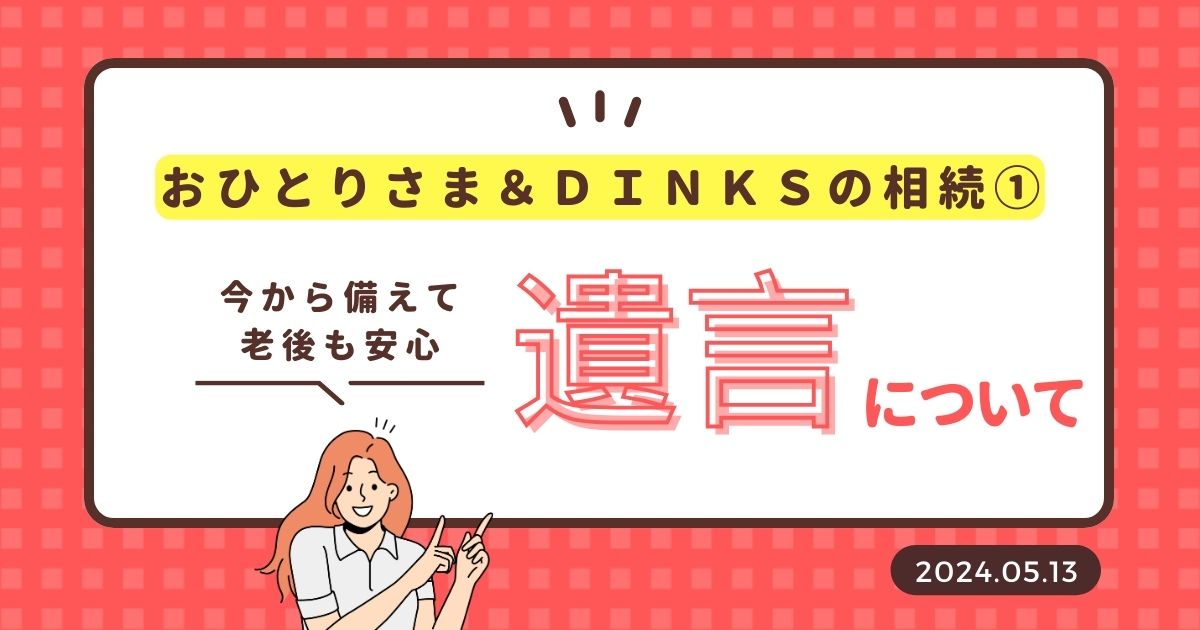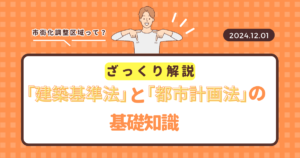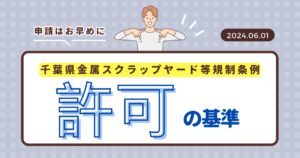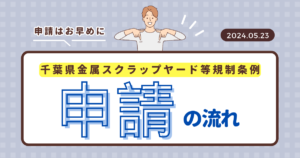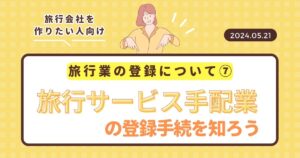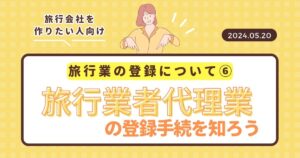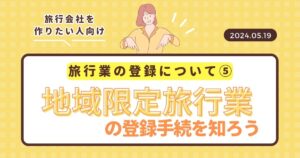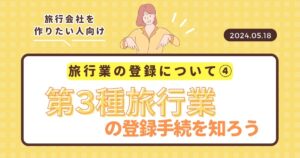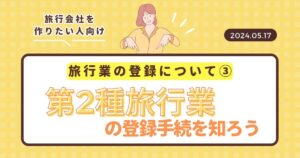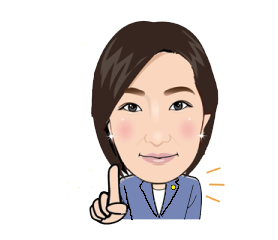
日本では近年、未婚者やDINKSが増加しており、相続問題が深刻化しつつあります。それでは、どのような問題があるのか見てみましょう!
相続問題が深刻化する理由は?
問題が深刻化する背景には生涯未婚率の上昇や少子高齢化による核家族化の進行があげられます。
国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、2015年時点の生涯未婚率は男性:23.37%、女性:14.06%と過去最高水準でした。内閣府の「男女共同参画白書」(2022年版)によると、2020年時点で推計された生涯未婚率は男性:30.4% 女性:23.1%となっており、生涯未婚率は年々高くなると思われます。
一方で、65歳以上の単独世帯も増加基調にあり、2020年国勢調査では、65歳以上の単独世帯は735万世帯と推計されており、更に2040年には約828万世帯に達すると予測されています。
このようなおひとりさま世帯やDINKS世帯が増加すると…
- 直系尊属や直系卑属がいない場合、遺産相続人がいなくなる恐れがある
- 兄弟姉妹がいる場合はその人たちが相続人になるが、縁遠い場合が多い
- 配偶者一人となった後に、配偶者にも直系の親族がいないと最終的に国庫に帰属する恐れ
- 事前の遺言書がないと、望まない人に遺産が渡ってしまう可能性
上記のような事態を引き起こすことが考えられます。これらの問題は生涯未婚率の上昇と高齢化が進行する中、おひとりさまやDINKSの相続問題は今後さらに深刻化することが予想されます。生前の対策が一層重要になってくるでしょう。その解決策としての手段の一つに「遺言書」があります。
遺言書を知ろう!
【遺言書のメリット】
・自分の意思に基づき、遺産の行く末を明確に指定できる
・法定相続分とは異なる遺産分割を行えるため、柔軟な対応が可能
・遠縁の親族ではなく、望む人に遺産を残せる
【遺言書の限界】
・作成を忘れた場合や内容に不備があると無効になる可能性がある
・家族間で遺言の有効性を巡って争いが起きるリスクがある
・公正証書遺言でない限り、将来的に書き換えや偽造のリスクがある
・遺産の範囲が大きすぎると、遺留分の侵害になり遺言が一部無効になるケースも
つまり、遺言書作成は有効な対策ではありますが、法的なリスクを完全に払拭できるわけではありません。
おひとり様やDINKSの増加に伴う相続問題に対しては、遺言書作成に加え、以下のような対策の検討も重要だと考えられます。
- 生前贈与などで遺産の範囲を狭める
- 資産の一部を寄付や遺贈で処分する
- 法的な検討を重ね、客観的にみて公正な遺言書を作成する
- 必要に応じて専門家に相談する
遺言書の種類
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの形式があります。
それぞれの特徴と違いは以下のとおりです。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人が全文を自筆で書き記した上で、以下の要件を満たす必要があります。
必要条件
- 遺言書に日付の記載が必要
- 遺言書に氏名の記載が必要
- 遺言者が、2人以上の成年者の立会人の面前で「これが私の遺言です」と宣言する
- 立会人2人以上が、その場で遺言書に署名捺印する
この要件を全て満たさないと、自筆証書遺言は無効となります。特に日付、氏名の記載漏れや立会人の不在、立会人の署名捺印がない場合は無効になりやすいので注意が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人役場で公証人の立会いのもと、遺言内容を宣言し、公証人がこれを作成する方式です。
作成手続き
- 公証人役場へ赴き、遺言の内容を公証人に口頭で伝える
- 公証人が遺言書の原案を作成し、遺言者にその内容を確認してもらう
- 遺言者が内容に同意した場合、公証人立会いの下、遺言者が遺言書に署名捺印する
- 公証人も署名捺印し、公正証書遺言が確定する
公正証書遺言は、確実性とプライバシー保護が最大のメリットです。一方で費用負担が嵩むのが難点です。
費用対効果を考慮し、重要な遺産の有無や遺言内容の複雑さなどによっては、この方式を選ぶ価値があるでしょう。遺言作成時の安心感を望むなら、この方式が最も確実性の高い選択肢といえます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者自身が遺言書を作成し、封をして公証人に預け、公正証書を作成してもらう方式です。
作成手続き
- 遺言者が自らの手で遺言書を作成する
- その遺言書を封をして封印する
- 公証人役場に赴き、封印した遺言書を公証人に預ける
- 公証人立会いの下、遺言者が「この封書は私の遺言書である」と宣言する
- 公証人がその発言を記録した公正証書を作成する
秘密証書遺言は、遺言内容の秘密にできることがメリットの一方で、手続きが最も複雑で費用もかさむ形式です。
遺言内容のプライバシー保護を最重要視する場合や、公開したくない遺言内容がある場合などに適した選択肢と言えます。しかしながら、手続きが複雑なので専門家に相談することをお勧めします。
【各遺言書の比較】
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 作成費用 | あまりかからない | かかる | かかる |
| 内容の機密性 | 保たれない | 保たれる (公証人は内容を知っている) | 保たれる |
| 手続の複雑さ | 簡単 | やや複雑 | 複雑 (遺言作成と公証手続) |
| 無効になる可能性 | 要件を満たさないと無効 | 公証人が作成するので安心 | 要件を満たさないと無効 |
自筆証書遺言書保管制度について
自筆証書遺言書保管制度をご存知でしょうか。
自筆証書遺言書を作成し、ご自宅等で保管をされている場合、紛失や相続人等の利害関係人による改ざん等のリスクがあります。この制度を利用すると、遺言書は「法務局」において適正に管理・保管されます。
メリット
- 遺言書の保管申請時に民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
- 遺言書は画像データとしても長期間適正に管理されます。
- 相続開始後に家庭裁判所の検認が不要になります。
この遺言書の保管の申請は、遺言者が手続きをすることができ、申請1件(遺言書1通)につき3,900円の手数料でできます。自筆証書遺言のみでは不安という方は、この制度も併せて利用すると安心ですね。
おひとりさま&DINKsの相続 – 遺言 – について説明しました。
遺言でお困りの場合にはTOMOE行政書士オフィスにご相談ください。