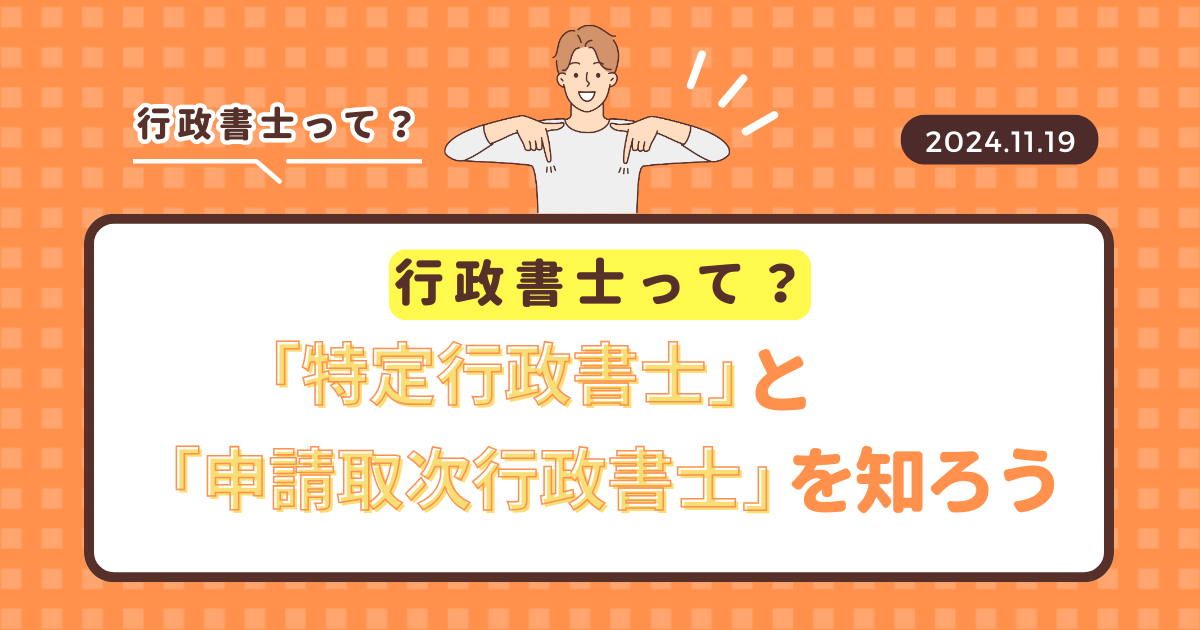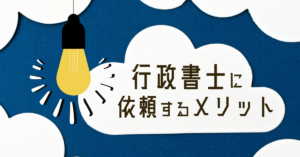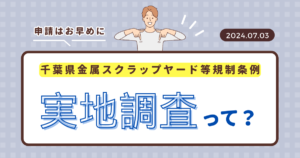こんにちは。行政書士の齋藤です。
先日、特定行政書士の考査の修了者の発表がありました。無事に考査をパスすることができました。
晴れて、特定行政書士となります。…とここまで書いて、一般の人には「行政書士」と「特定行政書士」の違いってわからないですよね。そして、他にも行政書士とつくものに「申請取次行政書士」というものがあります。
今回は、その違いについて説明していきます。
特定行政書士って?
まず、「行政書士」ですが毎年11月に行われる行政書士試験を合格するか、行政事務の公務員をある一定の期間務めると「行政書士」になることができます。この時点では、行政書士ではなく単なる資格を持っているだけですが、資格者が行政書士会に登録し、それが認められると「行政書士」になります。
行政書士になると、行政機関等に提出する多くの書類を作成したり、代理で申請したりすることができます。
では、「特定行政書士」は何ができるのでしょう?
「特定行政書士」になると、不服申し立てができるようになります。許認可等で不許可の場合などに、不服申し立てをすることができる行政書士が「特定行政書士」となります。(個人的には、しっかり許認可を取得できるに越したことはないと考えます。)しかしながら、何事にも「絶対」はあり得ませんから、万が一のときに特定行政書士だと安心かもしれませんね
特定行政書士になるにはどんな試験を受けるの?
特定行政書士は、既に行政書士として登録してる人が対象の考査となります。一定の研修を受けたのちに考査(試験)を受けます。内容は行政法と要件事実(民事訴訟法の一部)が出題されます。
2023年度から過去問は公開されていますが、それ以前の過去問はないので研修に使った資料と唯一(?)販売されている特定行政書士試験用の本で学習しました。
業務の合間だったので、そんなに時間もとれませんでしたが、考査を合格することができました。おそらく、行政書士試験合格後にあまり時間を空けずに考査を受けたのがよかったのかと思います。
目指される方は、合格後すぐがオススメです。
申請取次行政書士って?
申請取次行政書士も、既に行政書士として登録されている人が対象の考査です。この考査をパスして申請取次行政書士として登録されると「申請取次行政書士」として入管に書類を提出することができます。
在留許可申請や出入国に関わる入管業務では、必要な資格になります。
この「申請取次行政書士」は資格に有効期限があるのできちんと更新しないといけません。
申請取次行政書士になるのは難しいのか?
申請取次行政書士は、きちんと研修を受けていれば問題なく資格は取れると思います。
ただ、入管業務は奥が深く、申請取次行政書士を取得した上で更に知識を深めていく必要があります。
正しい在留許可か、そこに不正がないのかということも注意深く見極めていかなければいけないので、そういう感覚なども必要になります。
また、同じ在留許可の申請だとしても、申請者のバックグラウンドによって結果が変わってしまう場合もあるので、事前に丁寧な説明をしていくことも重要です。
例えば、AさんとBさんが同じ在留許可を取得するとします。同じ在留許可だからAさんが簡単に取得できたから、Bさんも簡単に取得できるわけではありません。個人の置かれている状況により、許可の取得の難易度が変わるため、経験も非常に大事です。
結論
不服申し立てをするときには「特定行政書士」に、在留許可の申請をするときには「申請取次行政書士」に依頼するようにしましょう。
TOMOE行政書士オフィスの行政書士 齋藤は、両方の資格を持っています。
何かありましたら、遠慮なくご相談ください。