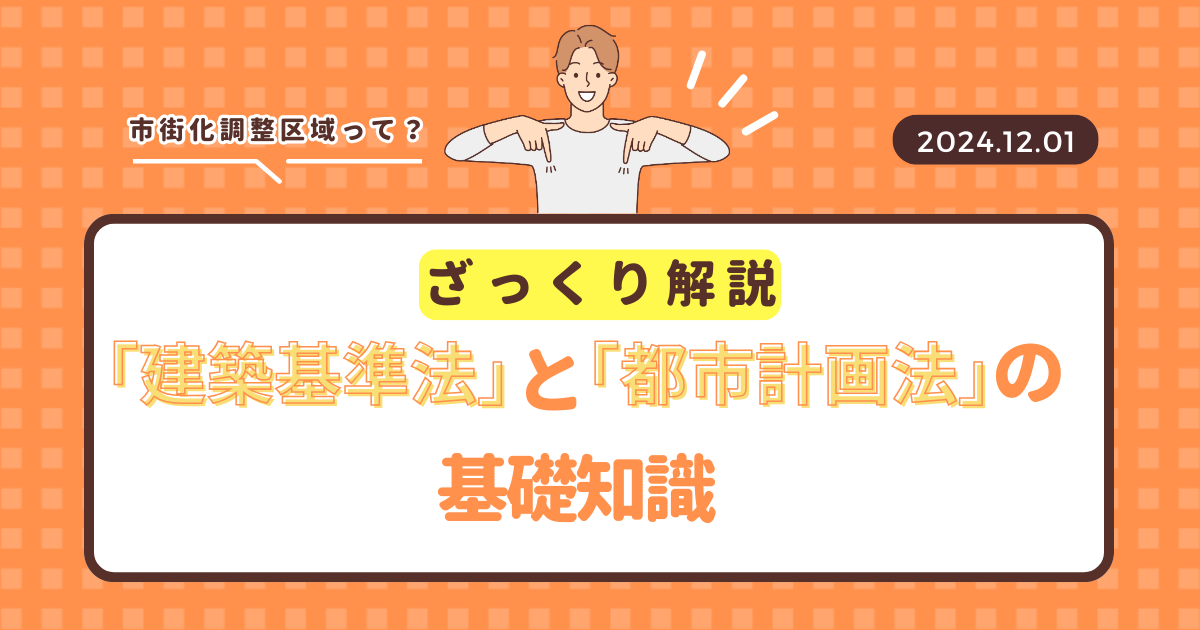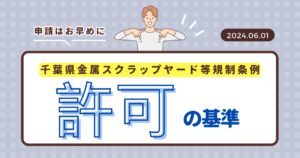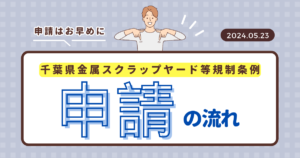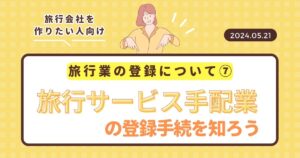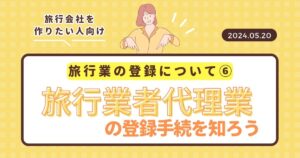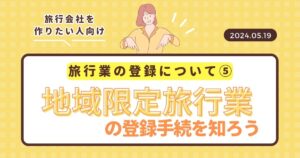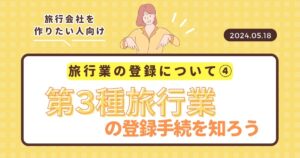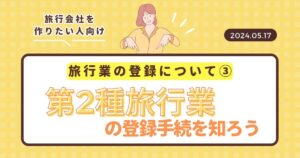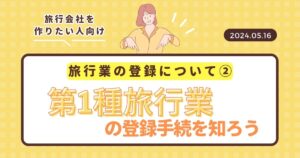こんばんは。行政書士の齋藤です。今回は、建築基準法と都市計画法の概要についてざっくり解説します。
日本における建物の設計や建築は、建築基準法と都市計画法の規定によって大きく影響を受けます。
これらの法律は、建物の安全性や住環境の向上、地域全体の調和を図るために不可欠です。
それでは、各法律の特徴を見ていきましょう。
建築基準法とは?
建築基準法は、建物の安全性、耐震性、防火性、衛生性などを確保するための基準を定めた法律です。
この法律は、個別の建築物に焦点を当て、建設計画や設計を規制する役割を果たします。
建築基準法の目的
建物の安全性や快適性を確保することで、住民の生活環境を守ります。
例: 阪神淡路大震災後に耐震基準が見直されるなど、災害対策が強化されています。
建築基準法のポイント5つ
1. 用途規制
建物の用途(例: 住宅、商業施設、工場)に応じた制限を設けています。
例えば、住宅専用地域では大型の工場を建てることはできません。
2. 構造基準
建物が地震や火災に耐えられるよう、柱や梁、壁などの構造に関する具体的な基準が規定されています。
3. 接道義務
建物は幅4m以上の道路に接していなければならないとされています。これにより、緊急車両が通行できる環境を確保します。
4. 建ぺい率・容積率
- 建ぺい率: 建物の占有面積と敷地面積の比率。
- 容積率: 延床面積と敷地面積の比率。
これらは、敷地の過密利用を防ぐための規制です。
5. 高さ制限
周辺の住環境や景観、日照権を守るため、高さ制限が設けられています。
都市計画法とは?
都市計画法は、地域の土地利用を適切に規制し、都市の健全な発展を目的としています。主に地域全体の調和や国土の有効活用を重視しており、建築基準法と相互に関連しています。
都市計画法の目的
都市計画法は、無秩序な開発を防ぎ、効率的な都市空間を作るために設けられました。
地域の特性に応じて、住居専用地域や商業地域などを細かく指定します。
都市計画法で規定される3つの重要ポイント
都市計画区域の指定
都市計画区域は以下の2つに分かれます:
- 市街化区域: 開発が進められる地域で、建物の用途や高さを規制する「用途地域」が指定されます。
- 市街化調整区域: 原則として開発を抑制する地域で、農地や自然環境の保全が重視されます。
用途地域
都市計画法では、住居系、商業系、工業系に分類された12種類の用途地域を定めています。これにより、建物の用途や規模が制限されます。
都市計画法における12種類の用途地域は、建物の用途や規模を規制するために指定される地域で、住居系、商業系、工業系の3つのグループに分類されます。それぞれの特徴を図にしてみました。
| 住居系 | 用途地域 | 主な建物用途 | 制限される建物 | 特徴 |
| 第一種低層住居専用地域 | 一戸建て住宅、小規模な学校・診療所 | 中高層建物・商業施設の建設不可 | 良好な低層住宅地の環境を保護 | |
| 第二種低層住居専用地域 | 一戸建て住宅、床面積150㎡以下の店舗・事務所 | 中高層建物・大型商業施設の建設不可 | 規制がやや緩く、小規模な店舗も許可 | |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅(マンション)、学校、病院 | パチンコ店、カラオケボックスの建設不可 | 住環境を守りつつ中高層住宅の建設が可能 | |
| 第二種中高層住居専用地域 | 住宅、学校、病院、床面積500㎡以下の店舗 | 大規模商業施設の建設不可 | 第一種より規制が緩く、商業施設の一部も許可 | |
| 第一種住居地域 | 住宅、中小規模のスーパー、事務所 | 工場、騒音施設の建設不可 | 住民の生活補助のために一部商業施設を許容 | |
| 第二種住居地域 | 住宅、商業施設 | 騒音を伴う施設(パチンコ店等)の建設も許可 | 住居と一部商業施設が混在可能 | |
| 準住居地域 | 住宅、車庫、ガソリンスタンド、ホテル | 騒音を伴う工場の建設不可 | 幹線道路沿いで自動車関連施設を含む商業利用が可能 | |
| 商業系 | 近隣商業地域 | スーパー、飲食店、小規模な事務所 | 大規模工場や危険物施設は不可 | 住宅地に隣接し、住民の利便性を図る地域 |
| 商業地域 | デパート、劇場、オフィスビル、大型商業施設 | 工場の建設には制限あり | 高度な商業活動を許可する地域 | |
| 工業系 | 準工業地域 | 工場、小規模な店舗、住居 | 環境を著しく悪化させる工場は不可 | 住居と工場の混在が許可される |
| 工業地域 | 工場 | 商業施設は制限、住宅は一部許可 | 工場の立地を優先し、商業施設や住宅は制限される | |
| 工業専用地域 | 工場 | 住宅や商業施設の建設不可 | 重工業や大規模工場を中心とした地域 |
地区計画
特定のエリアにおいて、地域の景観や環境を守るための独自ルールが定められます。
開発許可制度
一定規模以上の土地開発や建築を行う場合、都道府県知事などから開発許可を受ける必要があります。
市街化調整区域における開発許可
市街化調整区域は、原則として建物の建設が制限される地域ですが、一定の条件を満たせば開発許可が下りることがあります。
開発許可の条件
- 公益性のある施設(例: 地域の学校、保育園、診療所などは、公益性が高いとして許可が下りることがあります。)
- 農業従事者向けの住宅や施設。
- 地域の住民生活に不可欠な建物(例: 小規模な店舗)。
手続きの流れ
- 都道府県または市町村へ事前相談を行う。
- 許可申請書を提出し、審査を受ける。
- 許可後、建設を開始する。
違反時の注意
市街化調整区域内で無許可で建築行為を行うと、建物の撤去命令や罰則を受ける可能性があります。また、他法令(農地法や景観法)も確認する必要があります。
1995年の阪神・淡路大震災を受けて耐震基準が大きく見直されました。また、市街化調整区域の運用は地域によって細かい違いがあるため、自治体の指導に従う必要があります。
今回はざっくりと建築基準法と都市計画法について記事を書いてみました。
今、関わっている金属スクラップヤードの申請でも、市街化調整区域である場合には建物が問題になります。
都市計画法の区域指定と登記上の地目を同じだと思っていらっしゃる方も多かったので、少し説明いたしました。
参考になれば幸いです。