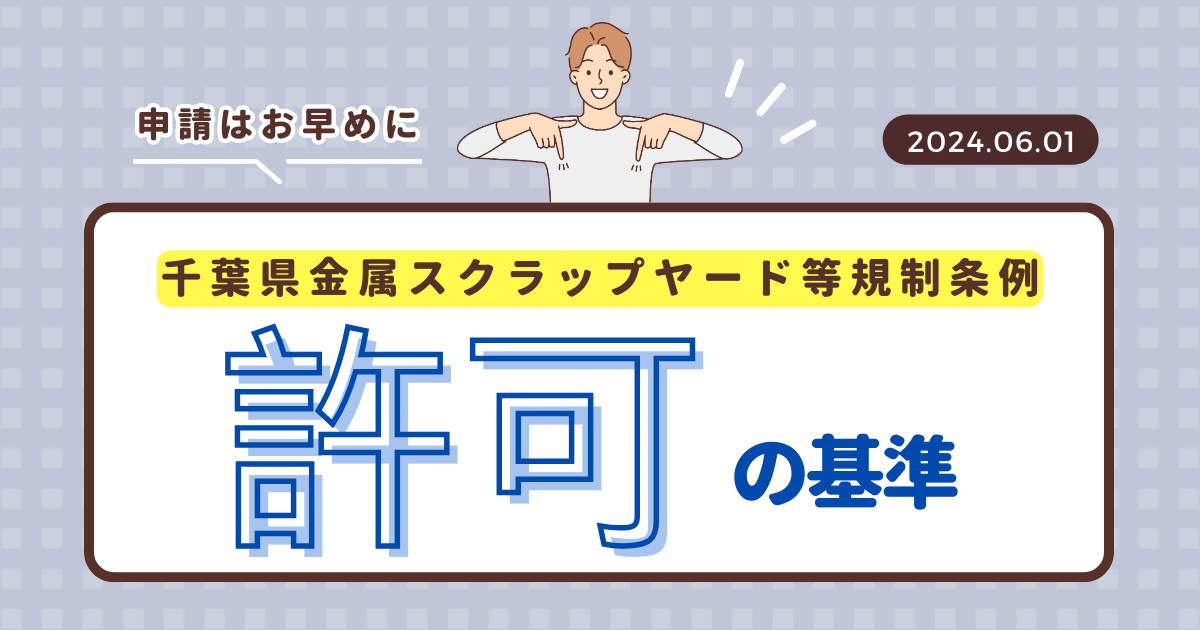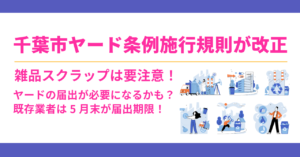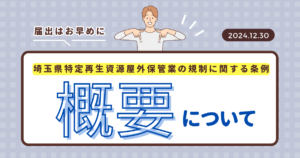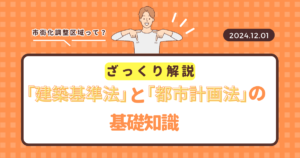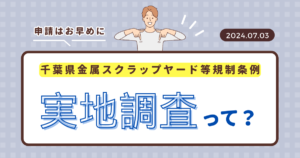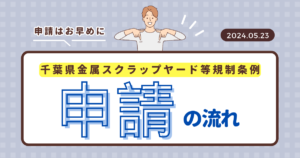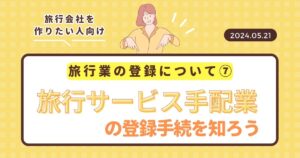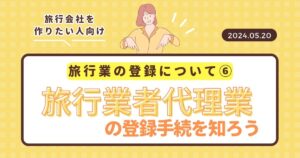千葉県で令和6年4月1日から施行された通称「金属スクラップヤード等規制条例」の対象となる「特定再生資源保管業」とは何か?また、どんな許可基準が設けられているのかを確認しましょう。
特定再生資源屋外保管業とは?
この条例では特定再生資源保管業とは次の要件に該当するものとしています。
- 特定再生資源の保管をする事業であること
- 屋外にて保管をすること
- 特定再生資源を重機等(ユンボ、バックホウなど)を使用して積み上げて保管していること
- 特定再生資源ってなに?
-
特定再生資源とは、本来の使用を終了して収集された製品・金属・プラスチックのことを指します。
※再利用を目的として取引されているものなどは含みません。
※製品の製造や加工、修理または販売、土木建築に関する工事などで出た金属の削りかすやプラスチック製品なども含まれます。規制対象外となるもの
①廃棄物
②みなし廃棄物
③有害使用済機器
④特定自動車部品
⑤放射性物質および放射性物質によって汚染されたもの - 屋根のある建物で保管する場合には対象にならないのか?
-
要件②における「屋外」とは「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物の外」と定義されております。屋根があっても、柱だけで壁がなく、風雨が入り込むような建物や仮設の小屋などは「屋外」と考えます。
- 保管物を自ら原材料として使用するのですが許可が必要でしょうか?
-
特定再生資源の保管が、原材料として使用するまでの間、自らの事業場で保管するような場合には、条例の規制対象になりません。許可は不要です。(この場合、原材料として使用するもののみ保管していることが前提です)
※使用するために選別や加工が必要となる場合には、「自ら使用するための一時的な保管」には該当しないため、許可が必要です。
- 既に市の条例で許可を取得しています
-
千葉市と袖ヶ浦市は独自に条例がありますので、そちらの条例が適用されます。
許可の基準について
許可申請の許可の基準としては下記の3つが挙げられます。
①事業者が特定再生資源保管業を行う事業者の義務を遵守すること
②申請者が欠格要件に当てはまらないこと
③住民説明会等を開催して周辺住民に事業を周知できていること
① 特定再生資源保管業を行う事業者の義務とは?
- 保管物の高さ
-
保管物が崩落したり、火災が発生したりするリスクを防ぐためには、高さ制限を守る必要があります。具体的には、保管物の高さが囲いの高さを超えないようにしなければなりません。例えば、雑品スクラップの場合、最高で5メートルまでの高さに制限されています。
- 廃棄物の適正処理
-
事業活動で発生する廃棄物は、廃棄物処理法に従って適切に処分する必要があります。これは、環境への影響を最小限に抑えるための法律であり、適切な処理方法が定められています。
- 囲いの設置
-
保管物が崩れたり飛散したりしないよう、保管場所の周囲に囲いを設置する必要があります。さらに、保管物の荷重が直接囲いにかかる場合、またはその可能性がある場合には、構造的に安全な囲いを設ける必要があります。
- 騒音・振動の防止対策
-
重機の稼働や保管物の積み下ろし、破砕作業などにより発生する騒音や振動が、周囲の生活環境に悪影響を与えないように対策を講じる必要があります。これには、防音壁の設置や作業時間の調整などが含まれます。
- 火災の発生防止① ~保管物の単位面積・間隔~
-
火災の発生や延焼を防ぐために、雑品スクラップの保管面積は一つあたり200㎡以内に制限し、保管物同士の間には2メートル以上の間隔を設ける必要があります。ただし、間に仕切りがある場合はこの限りではありません。
- 火災の発生防止② ~分別保管~
-
火災の原因となる可能性がある電池や油類、モーターなどは、適切に回収し、他の保管物と分別して保管する必要があります。これらの物品は屋内や不燃性の容器に入れて保管するのが望ましいです。
- 保管の場所
-
事業場内で保管場所を明確に設定し、特定再生資源の区分ごと(①金属スクラップ、②プラスチック類、③雑品スクラップ)に分類して保管する必要があります。
- 標識の掲示
-
事業の許可番号、事業者の氏名または名称、現場責任者の連絡先などの必要事項を記載した標識を設ける必要があります。これは、外部から見て事業内容や連絡先が明確に分かるようにするためです。
- 油等の流出・地下浸透防止
-
油や汚水が流出して地下に浸透し、公共水域や土壌を汚染することを防ぐために、保管場所の底面をコンクリートで敷設したり、油水分離装置や排水溝を設置するなどの対策が求められます。
- 現場責任者の設置
-
業場には、責任を持って現場の管理を行う現場責任者を設置する必要があります。現場責任者は、安全管理や環境保護に関する措置を適切に実施します。
申請手続における許可申請をする前に事前協議を行う必要があります。いきなり許可申請ではないのでご安心ください。既存の業者様に関しては早めに県と事前協議を行うことをお勧めします。(事前予約制)
令和7年3月31日までに既存の業者様においては、許可申請をしていないと事業が継続できなくなる可能性があります。それを避けるためにも、事業者様ご自身で申請をされる場合には早めに「事前協議」をお勧めします。(予約が徐々に埋まっているそうです…)事業者様自身が時間が取れないなどの理由がある場合には、お早めに行政書士に相談することをお勧めします。
ちなみに、大体の目安で事前協議が6か月、住民説明会(準備や周知期間等も含め)で1ヶ月半、約8か月後に許可申請にたどり着くのではないかと言われています(あくまで目安なので、事業者様によっては短くなったり、長くなったりすることも想定できます)。
② 申請者が欠格要件に当てはまらないこと
欠格要件とは
欠格要件とは、法律や条例により特定の資格や権利の申請者がその資格を得ることができない理由を示す要件のことです。金属スクラップヤード等規制条例における欠格要件は、事業の健全な運営と環境保護を確保するために設定されています。
- 禁固以上の刑に処せられてから執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経過しないもの
- 許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの
- 千葉県暴力団排除条例に規定する暴力団員ではないこと
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で法定代理人が上記の要件に該当するもの
- 法人の役員が上記の要件に該当するもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
③ 住民説明会等を開催して周辺住民に事業を周知できていること
住民説明会は事業の内容を周辺住民に知ってもらい、事業に関して理解を得るために行います。
- 対象となる住民は?
-
事業場の境界線からの水平距離が300m以内の区域に居住する住民に対して「住民説明会」を開催します
- 住民説明会の周知方法は?
-
住宅の戸数が少ないことが想定されるので、直接ポスティングや事業場やその近くの掲示板などでの掲示などが有効だと思われます。もし、周辺地域に町内会や自治会があるのであれば回覧板なども利用すると、より周知されます。
- 住民説明会の内容は?
-
① 事業者の名称・代表者の氏名
② 事業場の所在地・敷地面積
③ 事業場の構造及び設備
④ 保管の場所の位置及び面積並びに当該場所において保管をする特定再生資源の規則で定める区分
⑤ 保管物を積み上げる高さ
⑥ 破砕をする場合には破砕等の種類
⑦ 特定再生資源屋外保管業を開始する予定の日
⑧ 現場責任者の名前
⑨ その他知事が定める事項
①から③までの要件を満たすと許可がおりますが、各要件に細かく基準が定められています。
その細かい基準に調整していくために事前協議が行われます。
大事なことなので繰り返しますが、大体の目安で事前協議が6か月、住民説明会(準備や周知期間等も含め)で1ヶ月半、約8か月後に許可申請にたどり着くのではないかと言われています。
既存の業者様に関しては、8月までには事前協議を済ませておくことをお勧めします。事前協議には準備する書類等も多くあります。お早めに対応することをお勧めします。
お困りの場合には、お問い合わせください。